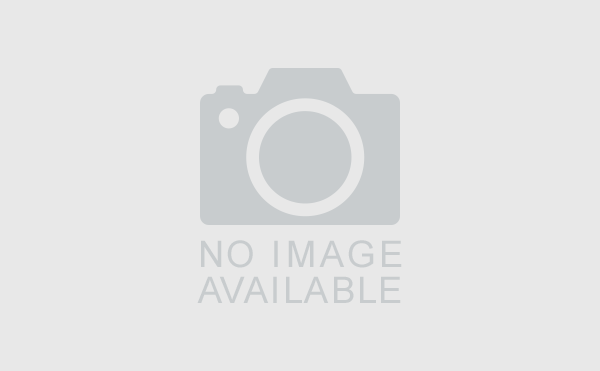錦帯橋・吉香公園

延宝元(1673)年、三代岩国藩主の吉川広嘉の創案で造られた錦帯橋(きんたいきょう)は、長い間、観光・岩国のシンボルとして親しまれている。春はサクラ、夏は鵜飼、秋は紅葉、冬は雪景色がこの優雅な橋に一層の趣を添え、吉香(きっこう)公園とともに四季折々の景観を楽しむことができる。3月下旬には約3,000本のサクラが咲き始め、岩国の春を彩る。
岩国の歴史は、慶長5(1600)年の関ケ原の合戦の時、吉川広家が西軍方であったため、出雲国富田14万石から岩国3万石に移封されたことに発する。初代岩国藩主の吉川広家はサクラが非常に好きだったと伝えられ、広島藩の上田宗箇にサクラを贈るなど、300年も前から岩国はサクラの名所であったとされている。
現在の錦帯橋畔・吉香公園のサクラは、明治18(1855)年に吉香神社が吉香公園に移築された翌年に、ソメイヨシノを植栽したことに始まると言われている。昔の人が「年々歳々花相似たり、歳々年々人同じからず」と詠んだこのサクラは、毎年変らず淡いピンク色に包まれ、人々の心を和ませている。3,000本のうち90%がソメイヨシノで、残りがヤエザクラ、シキザクラ、オオシマザクラとなっていて、歴史と伝統の町にふさわしく樹齢60~70年のものが多く、100年以上のものもある。日本三名橋の筆頭とも言える名勝錦帯橋とサクラとの調和は一幅の絵を見るような美しさで、背後の城山の常緑と相まって、あでやかな錦絵の世界と絶賛されている。
錦帯橋から歩いて5分くらいの吉香公園ではサクラがその短い命を終わらせたあともボタン、フジ、ツツジ、アヤメ、ショウブなどが次々と咲き乱れ、訪れる人々の歓声を誘う。