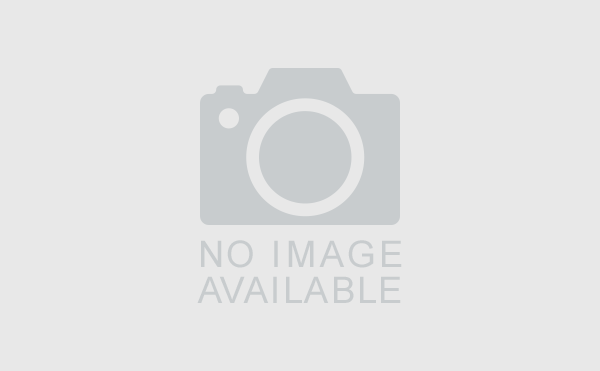大村公園

日本最初のキリシタン大名として有名な十八代領主大村純忠が没した後、その子大村喜前の手によって慶長4(1599)年に築城された玖島城(くしまじょう)。今日では石垣のみの姿となってしまったが、現在は3月下旬から咲き揃うサクラ、5月下旬からのハナショウブなど、花の名所「大村公園」として人々のやすらぎの場となっている。
公園入口バス停から1~2分歩くと見えてくるサクラの森。そこが九州でも有数の花の名所として知られる大村公園。ここにはおよそ2,000本のサクラが城跡のいたる所に立ち並び、春になるとその優美な姿を目当てに多くの人々で賑わいをみせる。中でも、4月上旬から中旬に咲く約300本のオオムラザクラは、国の天然記念物に指定され、その高尚優美な姿は訪れる人を魅了している。

オオムラザクラは、昭和16年、大村の女子師範学校の教官をしていた戸山三郎氏が多くのサトザクラ(ヤエザクラ)の中から発見し、学会に報告・命名された大変珍しい品種で、昭和42年に国の天然記念物に指定された。この花の大きな特徴は八重咲きの花が2つ重なった格好の2段咲きをすることで、驚くのはこの花びらが、少ないもので60枚、多いものになると200枚にも及ぶことだ。このことからも、オオムラザクラの豪華でボリュームのある美しい姿が想像できるだろう。
このほかにも園内には、ヤエザクラや、県指定天然記念物のクシマザクラがおよそ200本、ソメイヨシノが1,500本と、多くのサクラが春の訪れを知らせてくれる。